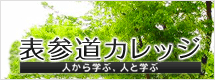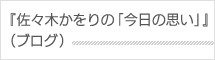会議番号:3785 開催期間 2025年11月07日- 11月14日
イー・ウーマン(ewoman)
働く女性の声を発信するサイト『イー・ウーマン』
- 取材のご依頼 | 講演のご依頼 | TV・ラジオ出演のご依頼 | お問い合わせ

生前贈与の注意点、ご存じですか?
皆様、今回もたくさんのご意見、そして具体的なご質問をいただき、ありがとうございました。「生前贈与の注意点を知っている(YES)」と回答された方は、最終的に23%となりました。
前回、「自...
>>議長コメントを全文読む
![]()
-

 NATO防衛費5%へ。日本への圧力、気になりますか?
日米の「関税交渉」が合意され、日本からの輸出品税率は、自動車を含め15%で決着し...
NATO防衛費5%へ。日本への圧力、気になりますか?
日米の「関税交渉」が合意され、日本からの輸出品税率は、自動車を含め15%で決着し...
-

 国会議員の女性割合、このまま低くて良いですか?
みなさん、「国会議員の女性割合、このまま低くて良いですか?」への投票、そして、「...
国会議員の女性割合、このまま低くて良いですか?
みなさん、「国会議員の女性割合、このまま低くて良いですか?」への投票、そして、「...
-

 日本の「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に。知ってましたか?
あっという間に最終日となりました。
今回のテーマ、『日本の「伝統的...
日本の「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に。知ってましたか?
あっという間に最終日となりました。
今回のテーマ、『日本の「伝統的...
-

 あなたは、リーダーシップがありますか?
2025年1月は、リーダーシップについて考えてきました。重要なポイントなどはDa...
あなたは、リーダーシップがありますか?
2025年1月は、リーダーシップについて考えてきました。重要なポイントなどはDa...
-

 相続について、家族で話し合っていますか?
会議に参加してくださったみなさま、1週間ありがとうございました!
今回は「相続...
相続について、家族で話し合っていますか?
会議に参加してくださったみなさま、1週間ありがとうございました!
今回は「相続...
-

 巨大地震への備え。ハザードマップをチェックしていますか?
いのちと暮らしを守るためには、正しく恐れて正しく備えることが欠かせません。
&n...
巨大地震への備え。ハザードマップをチェックしていますか?
いのちと暮らしを守るためには、正しく恐れて正しく備えることが欠かせません。
&n...
-
-1704867684.jpg)
 「日本版DBS」法案を閣議決定 。関心ありますか?
たくさんの投票と投稿をありがとうございます。
「イギリスのように、...
「日本版DBS」法案を閣議決定 。関心ありますか?
たくさんの投票と投稿をありがとうございます。
「イギリスのように、...

- ※イー・ウーマン ピアの方はここからログインしてください。
- 新規登録はこちら>>>
- ※旧リーダーズ/メンバーの方はここからログインしてピアに移行できます。
- イー・ウーマン ピアとは?>>>
 ライフイベントのタイミング
ライフイベントのタイミング 贈与の非課税
贈与の非課税